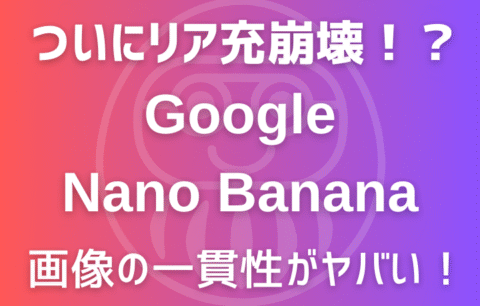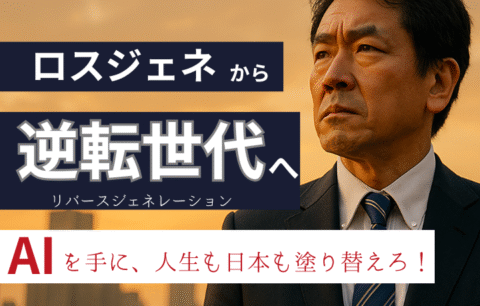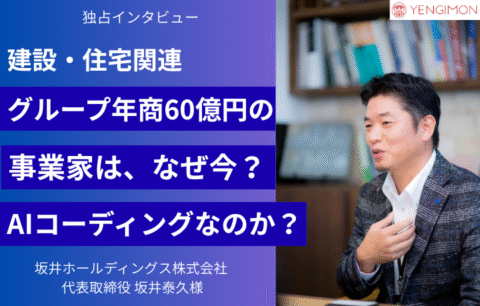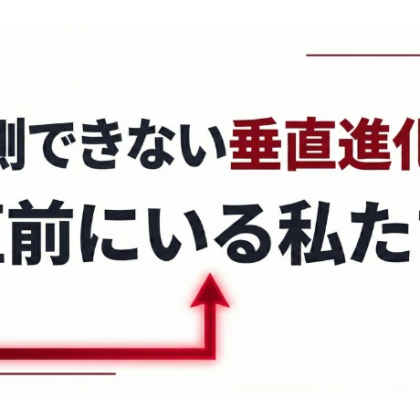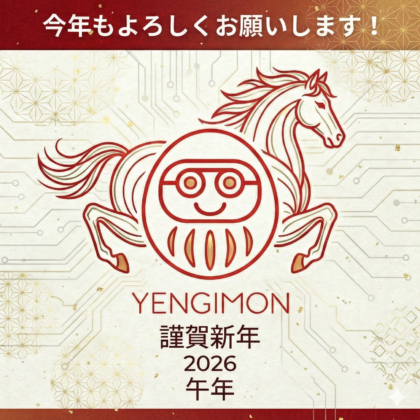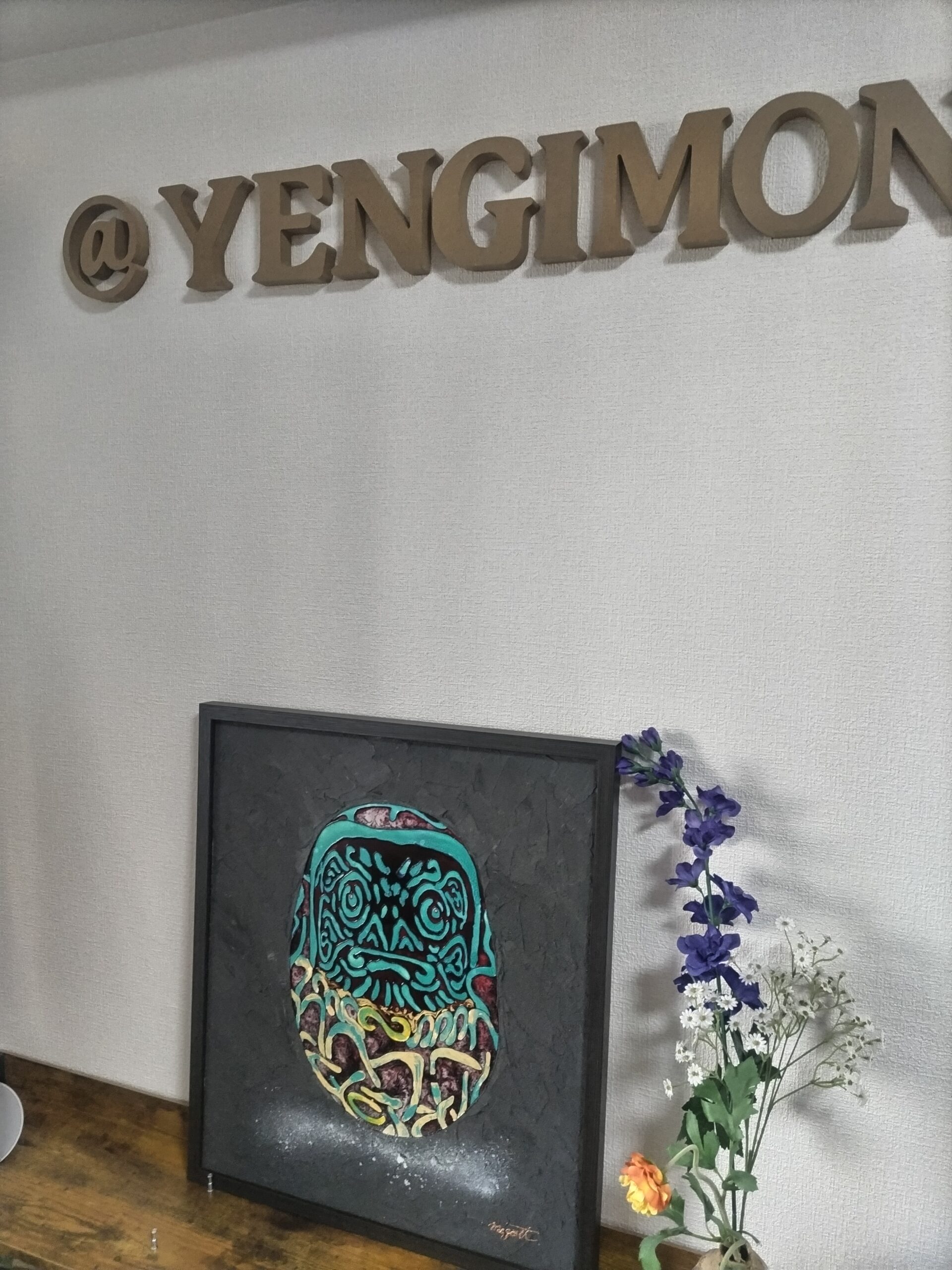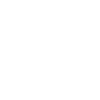2025年9月前半 生成AI関連ニュースのまとめ
はじめに:AIが再定義するビジネスの「常識」
本レポートでは、この転換期における国内外の主要な動きを詳細に分析します。まず、日本企業のAI活用が「ツール」の導入から「自律する戦力」の育成へとどう進化しているかを、具体的な事例を通じて解説します。次に、グローバル市場で巨大テック企業が繰り広げる、技術開発を超えたインフラ覇権争いと、それに伴う法的・倫理的課題の最前線を紐解きます。
第1章:国内市場の動向:AIは「ツール」から「自律する戦力」へ
日本市場では、生成AIをPoC(概念実証)から全社的な業務改革へとスケールアップさせる動きが加速しています。この章では、NEC、クレディセゾン、サイバーエージェントの具体的な事例を分析し、生成AIが単なる「効率化ツール」から「自律的に働く戦力」へと進化する様子を詳述します。
以下に、この期間の国内主要ニュースの概要をまとめます。
| 企業名 | 発表内容 | 主要な数値 | ビジネスへの影響 |
| NEC | AIエージェント技術「cotomi Act」発表 | 国際ベンチマーク「WebArena」で人間を超える80.4%の成功率を達成 | 熟練者の暗黙知を継承し、属人化しやすい業務を自動化 |
| クレディセゾン | 全社AI変革戦略 「CSAX」を発表 | 全社員3,700人をAIワーカー化、2027年度末までに300万時間の業務削減を目指す | AIを前提とした業務改革と組織文化の変革を推進 |
| サイバーエージェント | AIクリエイティブ BPOサービス開始 | クリエイター1人あたりの制作本数が、平均で月220本、トップクリエイターでは700本に増加 | クリエイティブ制作の効率が飛躍的に向上、業界の競争軸を再定義 |
1.1. NEC「cotomi Act」:暗黙知を継承するAIエージェントの衝撃
NECはウェブ業務を自動実行するAIエージェント技術「cotomi Act」を発表しました。この技術は、単に命令を処理するだけでなく、熟練社員のウェブブラウザ操作ログなどの行動履歴から、言語化が難しい「暗黙知」を自動的に抽出し、形式知化して学習する点が最大の特徴です。この機能により、AIは業務の背景にある文脈や意図まで理解し、曖昧な指示に対しても自律的にタスクを遂行できるようになります。
「cotomi Act」の性能は、国際的なウェブエージェントのベンチマーク「WebArena」において、80.4%というタスク成功率を達成したことで証明されました。これは、人間の成功率78.2%を上回り、世界で初めて人間を超越する画期的な記録とされています。
この発表は、単なるLLMの性能向上とは一線を画す、より大きなトレンドの最前線に日本企業が位置づけられたことを示唆しています。コンテンツ生成にとどまらず、自律的に行動を起こす「エージェントAI」への世界的なシフトが、この技術の根底にあります。日本社会が少子高齢化による労働人口減少という構造的な課題に直面している中、この技術は、属人化しやすい熟練者のノウハウをデジタル資産として組織全体で共有・継承するという、本質的な解決策を提示します。これは、製造業や金融業など、熟練の技が不可欠な産業にとって、生産性向上だけでなく事業継続性の観点からも極めて重要な意味を持っています。
1.2. クレディセゾン「CSAX戦略」:全社変革に挑む4つの柱
大手クレジットカード会社のクレディセゾンは、2025年9月1日に全社的なAI変革戦略「CSAX(Credit Saison AI Transformation)戦略」を発表しました。この戦略は、単なるAIツールの導入ではなく、全従業員3,700人全員を「AIワーカー化」し、2027年度末までに累計300万時間の業務削減を目指すという、組織全体にわたる大規模なものです。
この戦略の核となるのは、以下に挙げる4つの柱です。
- 全社員のAIワーカー化:
全従業員に「ChatGPT Enterprise」を導入し、AI利用を当たり前の文化として定着させます。実証実験では、参加者一人あたり年間100時間の業務削減効果が見込まれることを確認しており、この成果が全社展開の根拠となっています。 - 業務の再設計・AI起点の業務改革:
AIがあることを前提に、業務プロセスそのものを根本から見直します。人間が本来行うべき創造的で付加価値の高い業務に集中できるよう、AIによるアシストを前提とした業務設計を推進します。具体的には、2028年春までにAIコールセンターの本格稼働を目指しています。 - AIフレンドリーな情報・システム設計:
社内文書やナレッジベースをAIが構造的かつ意味的に理解しやすいように整備します。これにより、AIが迅速に社内データにアクセスし、パーソナライズされた顧客対応を実現できる環境を構築します。 - AIガバナンスの確立:
利用指針の策定、AIサービスの利用状況のモニタリング、リスク評価など、安全かつ倫理的なAI活用を担保するためのガバナンス体制を確立します。
クレディセゾンの事例は、AI導入の成功が「ツール」の導入そのものにあるのではなく、「変革マネジメント」にかかっているという重要な教訓を示唆しています。マッキンゼーのレポートも指摘するように、生成AIの真の価値は、従業員にAIを「共創」させる文化を築き、仕事のあり方そのものを再定義する「チェンジ・マネジメント」にあるのです 7。この戦略的なアプローチは、金融業界という機密情報を扱う難易度の高い分野において、ガバナンスと効率化を両立させる具体的なロードマップとして、多くの企業に参考となるでしょう。
1.3. サイバーエージェント:クリエイティブを「AI工場」で量産する新時代
広告事業を手掛けるサイバーエージェントは、AIを活用したクリエイティブ制作のBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)サービスを開始しました。このサービスは、AIと人間が密に連携することで、クリエイティブ制作の効率を飛躍的に高めるものです。
この取り組みにより、一人あたりの制作本数が従来の月30本から平均220本へ、トップクリエイターに至っては月700本にまで向上したと報じられています。AIが、広告画像のクリック率を予測したり、商品画像を多様な背景パターンで自動生成したりするなど、クリエイティブ制作のあらゆるプロセスを支援します。
この事例は、クリエイティブ業界におけるAIの脅威と可能性の両方を象徴しています。AIが単純な制作作業を代替することで、クリエイターは「手を動かす作業者」から「AIを使いこなし、アイデアや戦略を生み出すプロデューサー」へと役割を変容させなければなりません。AIを導入する企業が圧倒的な生産性を手に入れる一方で、AIを活用しない企業やクリエイターは、その生産性の差から競争力を失うリスクに直面します。これは、クリエイティブ業界に限らず、あらゆる職種に共通する課題であり、AIを使いこなす能力が個人のキャリアと企業の競争力を左右する時代が到来したことを示しています。
1.4. 日本企業における生成AI導入の現在地
日本企業の生成AI導入は、個別の先進事例だけでなく、産業全体に広がりを見せています。2025年版のJUAS(一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会)の調査によると、言語生成AIを導入している企業の割合は41.2%に急増し、前年からの大幅な伸びを記録しました。
しかし、その浸透度には大きな格差があります。
| 導入状況の比較 | 大企業(従業員1万人以上) | 中小企業(従業員1,000人未満) |
| 言語生成AI導入率 | 50.0%以上 | 15.7% |
| 特徴 | 専任チームを設置し、積極的な導入を推進 | リソースやノウハウ不足が課題 |
業種別に見ると、情報通信業(35.1%)や金融・保険業(29.0%)が先行している一方、人手中心の現場作業が多い卸売・小売業、運輸・郵便業、サービス業などでは導入が遅れがちです。
こうしたデータから、日本のAI活用において「大企業と中小企業のデジタル格差」が拡大している構図が浮かび上がります。大企業が大規模な投資と専任チームでAI変革を推進する一方で、多くの中小企業はリソース不足とノウハウ不足に直面しており、このままではAIによる生産性格差が産業全体の二極化を加速させる可能性があります。また、日本企業全体としては、安全性や倫理性を重視する慎重な姿勢から、段階的に導入範囲を広げる「スモールスタート型」が主流とされています。しかし、クレディセゾンのような大企業がガバナンスを確立した上で大規模な投資に踏み切ったことは、このトレンドに変化の兆しが見え始めたことを示唆しています。
第2章:グローバル市場の動向:覇権競争と倫理的課題の最前線
海外市場では、巨大テック企業によるAI覇権をかけた競争が、技術開発だけでなく、法務やインフラといったあらゆる領域で激化しています。この章では、Google、Perplexity、OpenAI/Oracleの事例から、その熾烈な戦いの実態を明らかにします。
以下に、この期間のグローバル主要ニュースの概要をまとめます。
| 企業名 | 発表内容 | 主要な数値 | グローバルな影響 |
| 画像生成モデル「Nano banana(Gemini 2.5 Flash Image)」をリリース | 公開からわずか1週間で2億枚以上の画像が生成 | 画像生成AIの用途を「アート」から「日常的な編集」へと民主化 | |
| Perplexity | 朝日新聞・日経新聞から著作権侵害で訴訟提起される | 3大新聞社が提訴、総額約44億円の損害賠償を請求 | AI時代の「情報の対価」と「フェアユース」の線引きを問う法的闘争が本格化 |
| OpenAI & オラクル | 5年間で3,000億ドル(約44兆円)のクラウド契約締結 | 契約に必要な電力は4.5ギガワット、約400万世帯分に匹敵 | AI覇権競争がインフラ投資へとシフトし、デジタル軍拡競争が加速 |
2.1. Google「Nano Banana」:画像生成AIの用途は「芸術」から「日常」へ
Googleがリリースした新しい画像生成モデル「Gemini 2.5 Flash Image」、通称「Nano banana」は、画像生成AIの用途を根本的に変える可能性を示しました。このモデルは、従来の画像生成AIがアート作品の創作に主眼を置いていたのとは異なり、写真をわずか数秒で超リアルな3Dフィギュアに変換する機能を備えています。また、複数の画像を融合したり、人物やペットの一貫性を保ったまま編集したりすることが可能です。
このツールは、誰でも無料で手軽に利用できる点が特徴で、公開からわずか1週間で2億枚以上の画像が生成されるなど、その利用率は急増しています。この動きは、画像生成AIの利用目的が「専門家によるアート作品の創作」から、「一般ユーザーによる個人的なアセット(デジタルフィギュア)の作成」へとシフトしていることを示唆します。
これは、エンターテイメント、製品デザイン、マーケティングなど、新たなビジネスの可能性を切り開くでしょう。
しかし、その一方で、AIが生成する「6本指」のような不自然な描写や、情報の不正確さ(ハルシネーション)問題は依然として残ります。これにより、AI生成物の「最終確認」という人間の役割は、これまで以上に重要になっています。AIが提供する手軽さと効率性を享受する一方で、その出力の品質を最終的に担保するのは人間の目であるという点を認識することが不可欠です。
2.2. Perplexityを巡る著作権訴訟:情報の「対価」を問う新局面
生成AI検索サービス「Perplexity」を巡る著作権問題は、この期間に新たな段階に入りました。読売新聞社、朝日新聞社、日本経済新聞社の国内大手3社が、相次いでPerplexityを著作権侵害で提訴したのです。
この訴訟には、主に以下の2つの重要な論点が含まれています。
- 「ゼロクリック問題」:
PerplexityのようなAI検索は、ユーザーの質問に対し、引用元を示しつつも、AIが回答を要約して表示します。これにより、ユーザーは元の記事をクリックして読む必要がなくなり、コンテンツプロバイダーであるメディア側の広告収入が減少するという問題が発生しています。 - 信用毀損:
AIの回答に誤った情報が含まれているにもかかわらず、引用元として新聞社の名前が表示されることで、新聞社の信用が傷つけられるという指摘もなされています。
この法的闘争は、AI時代におけるコンテンツのあり方と、その対価をどう支払うべきかというグローバルな議論を日本で本格化させたといえます。今後、AI企業がコンテンツプロバイダーとライセンス契約を結び、データの利用に対して正当な対価を支払う新たなビジネスモデルが形成される可能性があります。これにより、健全な情報流通とAI技術の発展の両立が目指されることになります。
2.3. OpenAIとオラクルの巨額契約:AIインフラ競争の規模とスピード
海外のAI市場では、技術の覇権競争が、それを支える「インフラ」の確保へとシフトしています。その象徴的な動きが、OpenAIとオラクルの間で締結された5年間で3,000億ドル(約44兆円)という巨額のクラウド契約です。この契約は、AIモデルの開発に不可欠な計算資源(GPU)を確保するためのもので、オラクルの現在の年間売上高をはるかに超える規模です。
この契約は、OpenAIとソフトバンクが構想する、総額5,000億ドルのAIインフラ構築プロジェクト「スターゲート計画」の中核をなすものと報じられています 。このプロジェクトに必要な電力は4.5ギガワットで、これは約400万世帯分の消費量に匹敵します。
この巨額の投資は、AIの覇権争いがもはやモデルの性能やアルゴリズムだけでなく、それを支えるバックグラウンドの計算資源、つまり「インフラ」の確保へとシフトしていることを明確に物語っています。これは、まさに「デジタル軍拡競争」と呼ぶべき状況であり、この競争を制する者が次の時代のリーダーとなるでしょう。同時に、AIデータセンターの膨大な電力消費は、環境負荷という新たな課題を突きつけ、企業はAI投資を推進すると同時に、この「エネルギー問題」にどう向き合うかという、持続可能な成長に向けた戦略を迫られることになります。
第3章:2025年、生成AI市場を動かす3つの潮流
個別のニュースを超え、市場全体を貫く3つのマクロトレンドを分析することで、ビジネスリーダーが今後数年の戦略を立てる上で不可欠な羅針盤が見えてきます。
3.1. 「エージェントAI」がもたらす業務プロセスの根本的再設計
エージェントAIは、単なる応答ツールではなく、自律的にタスクを計画・実行する「デジタルな同僚」として位置づけられます。NECの「cotomi Act」が「暗黙知」を学習してタスクを自動実行する事例は、このトレンドの最前線にあります。マッキンゼーのレポートも、成功したエージェントAIの導入は、ツール導入ではなく、ワークフロー全体を再設計することから始まると指摘しており、AIが業務の「部分」を担うのではなく、業務プロセスそのものを根本から変革する時代が到来したことを示唆しています。これは、AIを前提とした新しい働き方、新しい組織のあり方を構想する上で不可欠な視点となります。
3.2. データ学習の新たなフロンティア:「合成データ」の戦略的価値
大規模言語モデルの学習に不可欠な高品質なデータは、インターネット上の「井戸が枯渇」しつつあり、著作権問題も絡んで入手が困難になっています。この課題を解決するために、AIが自ら現実的なパターンをシミュレートして生成する「合成データ」が、新たな戦略的資産として注目されています。MicrosoftのSynthLLMプロジェクトのように、合成データはモデルトレーニングの効率を劇的に向上させ、今後のAI開発競争の鍵となるでしょう。これは、AI開発のパラダイムを根本から変え、データ不足や著作権リスクといった課題を乗り越える可能性を秘めています。
3.3. AI活用を阻む壁:信頼性(Trust)と変革マネジメント
AIのハルシネーション(誤情報生成)問題は、RAG(Retrieval-augmented generation)などの技術で減少傾向にあるものの、完全にはなくなりません。また、AIを全社的にスケールアップさせるには、従業員の抵抗やスキル不足を乗り越える「チェンジ・マネジメント」が不可欠です。クレディセゾンの事例は、技術的な導入と同時に、ガバナンスと社員のスキル育成を重視する戦略が、いかに成功の鍵となるかを示しています。今後、企業はAIの「信頼性」を確保するためのプロセス(評価・検証)と、社員の「AIワーカー化」を促進するための文化・制度設計に、より一層注力する必要があるでしょう。
まとめと今後の展望:ビジネスリーダーが今、注力すべきこと
2025年8月後半から9月前半にかけての動向は、生成AIが「実験段階」から「実用段階」へと移行したことを明確に示しました。国内企業はAIを「戦力」として業務プロセスに深く組み込み始め、グローバルではAIの真の競争軸が「インフラ」と「倫理・法務」へと広がりを見せています。
この激動の時代を生き抜くために、ビジネスリーダーが今、注力すべきことは以下の3点です。
- 「AIネイティブ」な組織文化の構築:
単にツールを導入するだけでなく、AIを前提としたワークフローを再設計し、全社員を「AIワーカー」へと育成することが不可欠です。AIを駆使できる人材を育成し、新しい働き方を許容する文化を醸成することで、組織全体の生産性は飛躍的に向上します。 - インフラ投資の戦略的見直し:
AIのコストと便益を長期的な視点で捉え、GPUや電力といった計算資源、そして高品質なデータ戦略への投資を加速させる必要があります。AIの進化はインフラの規模と直結しており、この領域への投資が、今後の競争力を決定づけるでしょう。 - リスクと倫理への先行的対応:
著作権や誤情報といった法的・倫理的リスクは、AI活用の規模が拡大するほど顕在化します。これらのリスクを管理するガバナンス体制を早期に構築し、技術的な導入と両輪で進めることが、持続可能な成長への鍵となります。
今後のAI市場は、技術の進化に加え、それを支えるインフラ、法務、そして「人」の変革が一体となった、より複雑なエコシステムを形成していくでしょう。この潮流を捉え、表面的なトレンドに一喜一憂するのではなく、その根底にある本質を理解し、自社の戦略に落とし込む洞察力が、今最も求められています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
AIを難しく語らない。
私たちは中小企業のAI活用・導入をサポートする会社です。
九州・福岡のAI関連のおすすめ業者をお探しの方は、ぜひ弊社にもお問い合わせください。
キャンペーンや、経営者向けのマンツーマン無料AI講習も実施しております。
お気軽にどうぞ!
YENGIMON株式会社
福岡商工会議所 No.11-0149275 、福岡市ふくおか共創パートナー企業
https://www.yengimon.com/
X: https://x.com/yengimon
LINE: https://lin.ee/Z5V7t3f