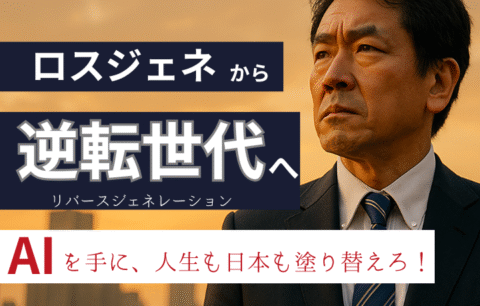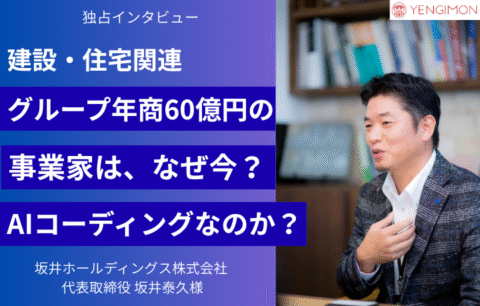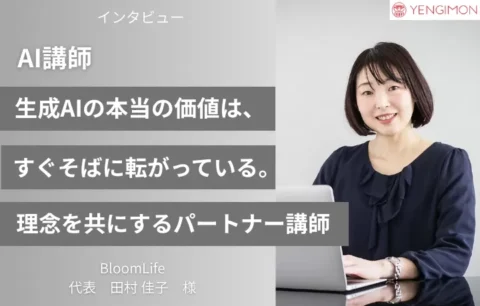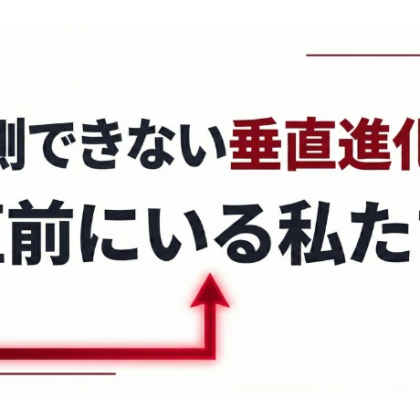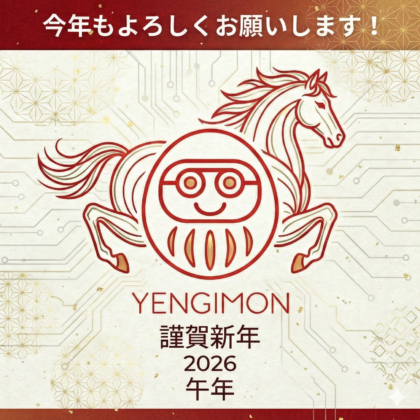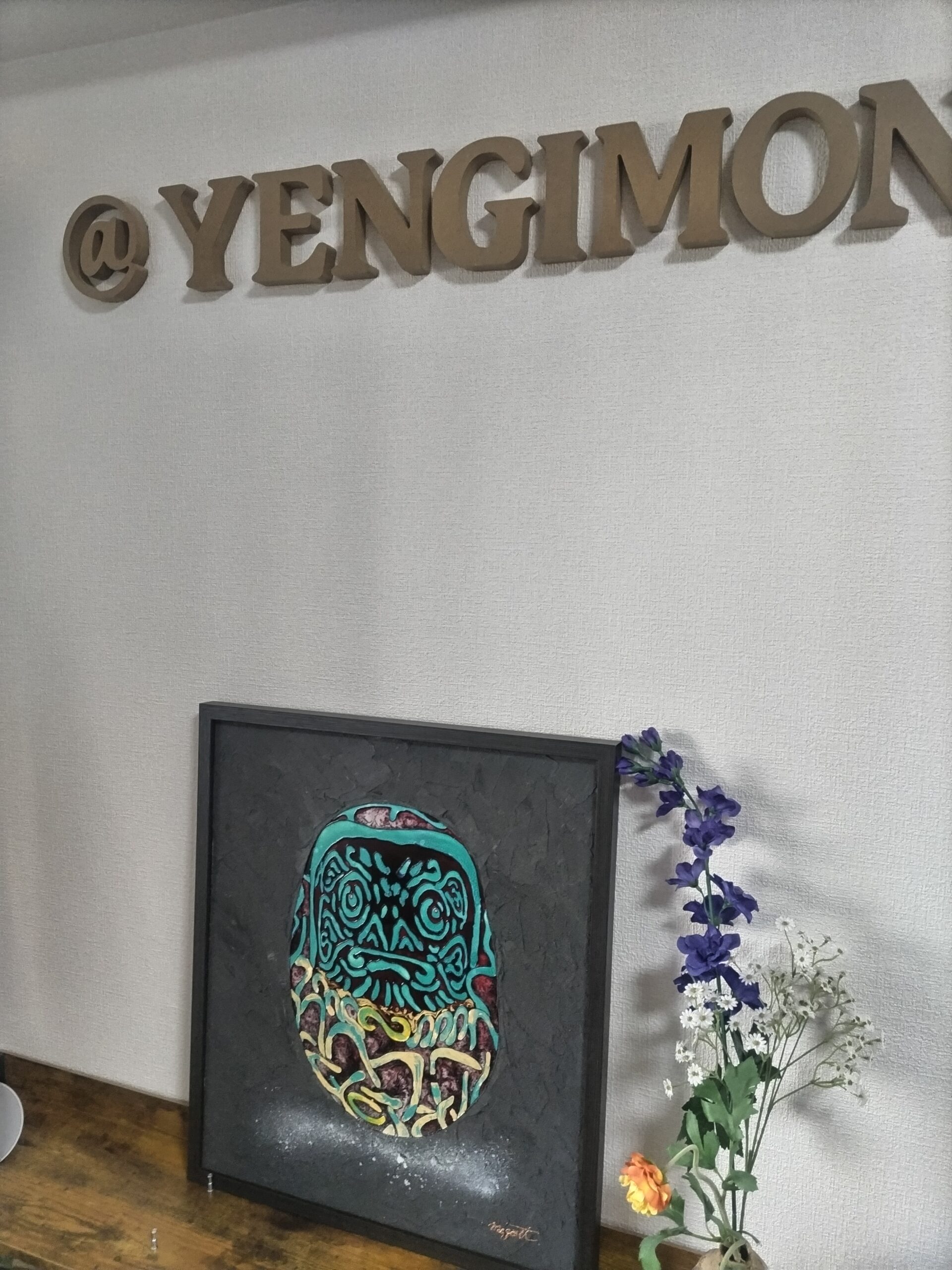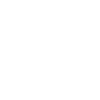【インタビュー・事例】継承者としての人生、中小企業の実情、伝統産業の可能性と未来、そして生成AIの活用をどう捉えているのか。サヌイ織物代表・讃井勝彦氏にお話しを聞いた。
- ”革新”という呪縛、その本来の意味とは。
- 「結局、何をやってるのかっていうと、今の時代のニーズに応えているだけですよ」インタビューは、このひと言から始まった。
- 「博多織は帯じゃない」 売上8割を捨てた先代の決断と、”革新”という言葉の罠
- 「地獄を見た人間は強い」 リーマンショック廃業寸前の記憶が、コロナ禍を乗り越える糧に
- 守るべきは「チャレンジ精神」。”HAKATA-ORI NEXT”に込めたリーダー産業への覚悟
- サヌイ織物はなぜ大手から選ばれるのか? 「入り口を変える」コラボ戦略と、大手と組むための「生産力」
- 後継者不足の真因は「親の苦労」。「デジタルの知識」不足と、若者が集まる会社の作り方
- AIは「こんぐらい」の感覚を理解できるか? ChatGPTに感じた「経験値のなさ」と、人間にしか生み出せない「感動」
- 「胸を張って言える産業に」 1000年先まで伝統を残すために、今、経営者がすべきこと
- まとめ(所感)
”革新”という呪縛、その本来の意味とは。
中小企業の経営者、あるいは新規事業の担当者であれば、「革新(イノベーション)」という言葉の重圧を一度ならず感じたことがあるだろう。伝統ある産業なら、なおさらだ。
「伝統を守りつつ、革新を起こさねば」——。
その強迫観念にも似たプレッシャーは、時に本質を見失わせる。
折しも、世界は生成AIの爆発的な進化という、新たな変革期を迎えている。
ChatGPTや各種生成AIツールが、ビジネスの前提を覆そうとする今、「AI活用」もまた「革新」の同義語のように扱われる。
しかし、本当にそうだろうか。
福岡・博多の地で、約800年の歴史を持つ伝統的工芸品「博多織」。
その世界で、ひときわ異彩を放つ経営者がいる。讃井勝彦氏だ。
先代が売上の8割を占めた帯事業を停止するという大胆な決断を下し、自身はリーマンショックで「地獄」を見た。そこから這い上がり、ポケモン、北斗の拳、レクサス、VANSといった、およそ伝統工芸とはかけ離れた分野とのコラボレーションを次々と成功させる。
本記事では、讃井氏が語る「革新なくして伝統なし」の真意、リーマンショックという極限の逆境を乗り越えた経営者としての強さ、そして生成AIが決して代替できない人間の領域について、その哲学を深く紐解いていく。
————————————————————————————————————
プロフィール
株式会社サヌイ織物代表取締役社長 讃井勝彦 氏
博多織製造販売、博多織工芸館運営
https://sanui-orimono.co.jp/
https://sanui-orimono.stores.jp/
約800年の歴史を持つ博多織を継承する企業の代表取締役。天皇陛下即位の献上品やISUフィギュアスケート国別対抗戦のメダルリボンなど数々の実績や表彰あり。
また、キン肉マン、ポケモン、レクサス、VANSなど異業種とのコラボレーションを積極的に展開。「博多織を知ってもらう」ことを第一に、時代が求めるニーズに応え続ける経営を実践。生成AIなどの新技術に対しても好意的かつ冷静な視座を持つ。
————————————————————————————————————
「結局、何をやってるのかっていうと、今の時代のニーズに応えているだけですよ」
インタビューは、このひと言から始まった。
「博多織は帯じゃない」
売上8割を捨てた先代の決断と、”革新”という言葉の罠
多くの人が「博多織」と聞けば、着物の「帯」を連想する。しかし、讃井氏はその固定観念こそが、本質を見誤らせる源だと指摘する。
「結局、博多織って何なのっていう、そもそも論になると思うんですけど。博多織っていうのは、織物なんですよ。帯じゃないです。織物の中に帯という商品もある、ということです」
歴史を紐解けば、その事実は明らかだ。1241年に博多織が始まったとされるが、帯が開発されたのは1540年頃。実に300年間、博多織は帯を織っていなかった。徳川幕府への献上品も、文献を調べれば帯以外のもの、例えばタバコ入れや巾着、こたつかけなども多く存在したという。
「たまたま帯が売れてた時代がありましたので、帯しか作らなかった。帯だけ作っていけば食べれてたからですね。でも、帯を織らないということ自体は、不思議なことでもなんでもないんです」
讃井氏の先代(父親)は、会社の売上の8割を占めていた帯の生産を停止するという大きな決断を下した。
当時、博多織イコール帯という社会的イメージが強固だった時代だ。
「アホだと言われたでしょうね」と讃井氏は振り返る。
この先代の決断は、今の経営にどう受け継がれているのか。「創造性」や「革新」といった言葉で尋ねると、讃井氏は意外な言葉を口にした。
「テレビなんか見てても、いろんな特集で必ず『革新』という言葉を使います。なんかいい言葉じゃないですか。いかにも新しいことやってますよ、みたいな。こんなのただの逃げ口上かなって私は思うし、これを言っておけばなんかすごいと思われるだけなんじゃないかなと」
「革新」という言葉の響きの良さに酔うのではなく、ただ現実を見据える。讃井氏の哲学は驚くほどシンプル。
「何をやってるのかっていうと、今のニーズに応えてるだけです。時代とともに、ニーズってかなり変化します。だから昔のものを昔のまま作って織るのが”伝統”とかで、ちょっと違うものを作ったら”変態”とかって言われる。その”変態”をやり続けると『あそこは革新だね』とか言われるっていうことなんでしょうけど。いわゆるその時代に合わせたニーズに応えてるだけなのかなっていう風には思います」
インターネットの普及、スマートフォンの登場。それらも社会のニーズに応えた結果であり、帯を作るか作らないか、柄を今風にするか否かという表面的な話ではなく、「もの自体が今風」という、ただそれだけのことなのだと。
陥りがちな「革新」という名の呪縛。その言葉がもたらす思考停止を鋭く見抜き、「世の中のニーズに応えていこう」という極めて実務的な視点に立ち続けている。
「地獄を見た人間は強い」
リーマンショック廃業寸前の記憶が、コロナ禍を乗り越える糧に
ニーズに応え続ける。その言葉の裏には、壮絶な経験があった。
リーマンショック。
讃井氏は、この未曾有の危機で「地獄を見た」と語る。
その経験が、今の経営の糧になっていることは間違いないという。
「地獄見てる。簡単に言いましたけど、やっぱこの経験って、ちょっともう言葉にしがたいぐらいの経験ですよ。それを見てる経営者は強いかなって」
数年で交代する“サラリーマン社長”とは違う。
家族経営で、好むと好まざるとに関わらず会社を背負う中小企業の経営者。廃業寸前まで追い詰められた状況は、まさに地獄だった。
「あのリーマンショックっていう、本当に廃業寸前の、従業員までもが敵のような目でね、会社を見てるっていうような状況。もう明日支払うお金がないみたいな、そういう状況から考えると、新型コロナ、ここもね、怖いなとは思いましたけど。やっぱりなんとか乗り切れました」
極限を越えてきた人間のひと言は重い。
守るべきは「チャレンジ精神」。
”HAKATA-ORI NEXT”に込めたリーダー産業への覚悟
同社は「革新なくして伝統なし」という哲学を掲げているが、約800年の歴史の中で「絶対に忘れないマインド」とは何なのだろうか。
「間違いないものを作ること。私、いろんな講演なんかでも、博多織ってなんなのって言われた時に、『博多で織られ続けている素晴らしい織物です』と答えてます。形が帯じゃないといかんとか、こうでないといかんっていうのはなくて、『素晴らしいもの』という表現以外はないと思います」
品質への絶対的なコミットメント。それがまず一つ。そして、もう一つ挙げたのが「チャレンジ精神」だった。
「先輩たちが築き上げてきたチャレンジ精神。そしてそれに対しての敬意ですね。ものづくりの中で、先輩たちは、やっぱりいろんなものを作ってきてるんですよね。その精神だけは忘れてはいけないと思います」
この精神は、「HAKATA-ORI NEXT」というスローガンにも表れている。
「私の場合、『博多のリーダー産業へ』って意味合いで使ってます。要は、もつ鍋とかラーメン、明太子、水炊き、こればっかりが元気じゃダメだと。実は、福岡で一番古い産業が博多織なんですよね。博多という名前がつくもので一番歴史がある産業は博多織なんです」
博多祇園山笠よりも1年長く、産業としては最も古い「博多織」。
その名を冠する限り、リーダー産業でなければならない。
その覚悟が、「HAKATA-ORI NEXT」という言葉に凝縮されている。
サヌイ織物はなぜ大手から選ばれるのか?
「入り口を変える」コラボ戦略と、大手と組むための「生産力」
讃井氏の「チャレンジ精神」と「ニーズへの適応」を最も象徴するのが、ポケモン、キン肉マン、北斗の拳、レクサス、VANSといった、多彩なコラボレーション展開だ。伝統工芸のイメージを覆すこれらの取り組みは、何を目的としているのか。
「まず入り口を変えることっていうのが一番の目的です。様々なキャラクターのファンの方に、博多織っていうことを知ってもらえる。博多織の商品ではなく”〇〇の商品が博多織であること”の違い、その入り口が違うんですよね。訴求する相手が違います」
目的はただ一つ、「博多織をいろんな方に知ってもらうため」。 そして、同時に「技術力」を知ってもらう狙いもある。キャラクター物の監修は非常に厳しく、その厳しい基準をクリアできる技術力が博多織にあることを示すことにもなる。
こうしたコラボ戦略の中で、特に効果的だった事例として讃井氏が挙げたのは、レクサスやポケモンといった「大手」との取り組みだ。
「レクサスが求める高品質の製品を作らないといけない。これは耐久性なんかももちろんそうですけど。それと同様に重要なことは生産力。スケールが桁違いの量に対応していかないといけない。生産力もレクサスが求めるものなんですよ」
「質は良いけど一ヶ月に1個しかできません、じゃどうにもなりません」と讃井氏は言う。品質はもちろんのこと「一ヶ月に何万個できます」というレベルの生産力が求められる。伝統的工芸品が「産業」として在り続けるために必要なミッションでもあった。
「伝統的工芸産業というからには、産業。儲からないといけないですし、たくさん作って、雇用も生んで、儲かって、たくさん税金も納める。ここがやっぱり産業たるゆえんだとは思います」
この「産業」として伝統工芸を盛り上げるという覚悟が、大手との取引を可能にする。
大手の販売力、企画力、宣伝力は圧倒的だ。しかし、その土俵に乗るためには、彼らが求めるレベルの「技術力」と「生産力」、そして「間違いないものを作る」という覚悟が不可欠なのである。
後継者不足の真因は「親の苦労」。
「デジタルの知識」不足と、若者が集まる会社の作り方
伝統工芸の世界では、常につきまとう課題がある。高齢化、後継者不足、技能継承の困難さだ。現在の課題を尋ねたところ、真っ先に返ってきたのは意外な答えだった。
「まあ、知識でしょうね。デジタルの」
人材不足や技能継承よりも先に、「デジタルの知識」が課題だというのだ。
「今こうやってAIとか、そんな技術がたくさん開発されて、しかも安く使えるじゃないですか。ただ、使い方がわかってない。もっと自分たちの仕事に使えるように、まずは勉強しないといけないと思います」
デジタルに詳しい人間を雇い入れ、その人に博多織を学んでもらうか。現従業員がデジタルを学ぶか。「どっちが先か」という問題はあるにせよ、まずは「理解」と「勉強」が不可欠だと強調する。SNSを使うのでさえ二の足を踏んでいるレベルでは、生成AIをいきなり全社導入したところでおぼつかない。
この「デジタルの知識を勉強すること」こそが、時代(ニーズ)に追いつくために今、最も必要なものだという認識だ。
では、一般的に言われる「後継者不足」についてはどう考えているのか。
「結局は、親が苦労してるのを見せてるからなんですよ。だから子供は継ぎたくない。家族経営の会社って全部そうです。家に帰って、子供と晩御飯食べようという時間でも、『明日の支払いどうする』『お金ないよ』とか、そんな話題ばっかりですよ」
毎日そんな姿を見せられれば、子供が家業を嫌になるのは当然だ。大学まで行かせてもらったら、別の場所で就職しようと考える。それが、我が国の後継者不足の構造的な原因だと讃井氏は喝破する。
「だから子どもたちに、それは我が子じゃなくても、若い人たちにもっともっと魅力がある会社っていうのを作らないといけないですし、その魅力を発信しないといけないんです」
魅力的な会社を作り、それを発信する。同社はそれを実践している。
だからこそ、「小学校の時からここで働きたいと思ってました」という若者が、サヌイ織物に面接にやってくる。
「そういうのを面接で言われたら、もう即採用しますよ(笑)。『あなた何がしたいと』とか『何ができると』って聞く前からもう。そういう子が何人もいます、うちには」
魅力の発信源は、讃井氏自身が「知ってもらうこと」を第一に、体当たりで続けてきた活動にある。結果、小学生から老人会まで、毎日のように工場見学に訪れる。そして、自ら説明に立つ。そうした姿勢が、次世代の心を掴んでいるのだ。
AIは「こんぐらい」の感覚を理解できるか?
ChatGPTに感じた「経験値のなさ」と、人間にしか生み出せない「感動」
デジタルの知識が課題と語る讃井氏は、昨今の生成AIブームをどう見ているのか。ChatGPTなどを初めて触った時の印象を尋ねた。
「まだまだだなと。AIの知識っていうのはネット上にあるものでしかないでしょ。だから実際の経験値っていうのがない」
ネット上には嘘も本当も、極端な情報も混在している。たとえ今後、その真実性を見分ける能力を持ったとしても、それはあくまでネット上の知識に基づいたもの。「現場の経験」、つまり「やってみないとわかんない、こっちの方がいいやん!」という感覚的な判断は、AIには難しいのではないか、と指摘する。
一方、ここ最近の進化、例えば自然な音声会話などには驚きも感じているという。
「YENGIMONさんに教えてもらったGoogleのNotebookLM(AIが読み上げるラジオ番組風掛け合い音声)は、さすがにすごいなと思いました。話し方とかね、ああいったものはもう本当、人間が喋るのに近づいてますよね。本当に違和感がない」
では、AIがどれだけ進化しても、人間にしか担えない領域とは何なのか。讃井氏は即答した。
「感動。人を感動させることなんですよ。心を動かす」
AIにデザイン開発、品質管理、販売促進を任せれば、ネット上の流行などを組み合わせて「そこそこのもの」はできるだろう、と讃井氏は言う。
「でも、そんなの真似でしかないでしょう。今あるものを模したところで、人が感動するのかどうなのか。『いいね、これ』って、『よかったね』って思ってもらえるものを作らないと、人は買いません」
感動。それこそが人間の領域だ。そして、その感動を生み出す源泉には、AIにはデータ化できない、ある「感覚」が存在するという。
「今まで作ったものの作り方みたいなものは、デジタルで全部管理できると思います。ただ、その時のなんか『こんぐらい』っていう、なんか具合。管理しようがないことって、たくさんあると思うんです」
料理でいう「耳たぶぐらいの硬さ」といった微妙な「こんぐらい」。それは、仕事に長年携わっている人間だからこそ分かる感覚でもある。
「将来的にAIがもっと進化すれば、ものすごく使いやすいものにはなるんだろうと思いますし、まあ、いよいよ人間がいらなくなるかもしれないですけどね。でも、なんか『こんぐらい』っていうのがあるんですよ。しかもこれは毎日どんな業務でも皆が感じている感覚です」
この「こんぐらい」の暗黙知を、AIが真に理解できる日は来るのか。
また、従業員や職人たちが生成AIのような新技術に抵抗感を示すことがあるとすれば、それは単に「やってないから苦手」なだけだと讃井氏は分析する。
「スマホやLINEはみんな使っている。『苦手だから』とか『今の仕事が忙しい』とか、できない理由を並べる。でもそれじゃいかんと。これも仕事だからって」
生成AIによる動画編集一つとっても、苦手だからと放置すれば、旬を逃してしまう。
いきなり導入すれば拒否反応が起きるだろう。しかし、「こんなに便利になる」という楽しさと知識を高めていけば、特に生産管理などはデジタル化によって格段に楽になるはずだ。
「胸を張って言える産業に」
1000年先まで伝統を残すために、今、経営者がすべきこと
インタビューの最後に、今後挑戦したいこと、そして「1000年先に残す」という使命について尋ねた。讃井氏の答えは、これまで語ってきた哲学に、再び収斂していった。
「私自身、会社を継いで一貫してやっていることっていうのが、最初から話してますけど、博多織を知ってもらうこと。これが一番大事なことだと思って今もやり続けてます」
ネット・SNSでの発信、リアル店舗、目を引く看板。あらゆる手段を使い、体当たりで「知ってもらうこと」を実践し続ける。その先に見据えているのは、次の世代だ。
「若い人たちが、将来ね、県外、もしくは海外に行った時に、自分の故郷のことを話す機会がある時に、『私の町には博多織っていうのがあるとよ』って、胸を張って言ってもらえるような産業にしなければならないんです」
それさえできれば、1000年先、2000年先にも博多織は必ず残っていると信じている。 そのためには、博多織が「当たり前に使われている日常」を作ること。みんなが使いやすいものを作ること。知ってもらうこと。
結局、すべては「一貫」していた。
最後に、同業種の経営者へのメッセージを求めると、讃井氏はまず「苦しいですよね」と本音を漏らした。
「なんで経営者ってこんなに苦しいんだろうかなって思います。きついですよ。言われたこと一生懸命やって、お給料確実にもらえた方が、楽かもな、と思ったりもします」
従業員と経営者では、会社を見ている角度が180度違う。給料日には「もらえる人」と「払う人」に分かれる。その立場の違いは「孤独」とも隣り合わせとなる。
「時代が求める会社経営をしなければ、この先もね、もっと苦しいだろうと思います。で、難しいですよ。『変える』っていうのは。今まではこうでしたよ。でも今からはこうですよ、と。うまく受け入れていただけるような、ソフトな改革をしないといけない。急にいっぺんに変えると、そこには必ず痛みが伴います」
この「ソフトな改革」は、痛みを知りながらも、先頭に立って自ら時代のニーズをつかむために変化してき讃井氏だからこそ出た、思いやり溢れるワードだと感じた。
「このままじゃいけないと思うのであれば、やっぱり一歩一歩、時代が求める方向に行くべきじゃないのかなと思います」
最後に、YENGIMONに対してもメッセージをいただいた。
紹介するのはこれだけにしておこう。これだけで十分だ。重みのあるひと言。
「今後もAIのこと、もっと教えてください。」
まとめ(所感)
讃井氏が何度も口にした言葉は、「知ってもらう」だ。
正直、意外だった。 博多織は全国でも有名で、海外でも人気を集めている。そんな何百年も続く産業の会社トップが、なおも「知ってもらいたい」と、今日も体当たりで実践している。
「苦難」を原体験として持つからこそ、「ニーズへの適応」という現実的な戦略を徹底する。そこには、流行りの経営理論やAI活用論のような浮ついたものは一切ない。自らの仕事を「産業として存続させる」、あるいは「若者が胸を張れるもの」にするために、ひたすらに時代が求める方向へと適応し続けてきた経営者の、無骨なまでのリアリズムがそこにはあった。讃井氏の発言は、終始、「合理的」で「一貫」していた。
その視点は、生成AIに対しても揺るがない。「人間が築き上げたもの vs AI」という安易な対立構造をよそに、自社の課題は「デジタルの知識」と即答する。ただそれは、生成AIをあくまで「現代の道具」として冷静に捉えているからであろう。
「知ってもらうこと」は、単なる広報ではなく、産業として存続するための本質的な事業活動そのものだ。ご自身では「時代に合わせてるだけ」と謙遜されるかもしれないが、その「合わせ続ける」ことへの一貫した実践こそが価値を生み、1000年先までの道を守り、創っているのだと感じた。
取材日時:2025年10月某日
取材・編集担当:YENGIMON株式会社 永江
Thank you by
株式会社サヌイ織物 代表取締役社長 讃井勝彦 様
ホームページ:
https://sanui-orimono.co.jp/
公式オンラインストア:
https://sanui-orimono.stores.jp/
インスタグラム:
https://www.instagram.com/hakataori.sanui/
facebook:
https://www.facebook.com/sanui.orimono
X:
https://x.com/sanui_orimono
You Tube:
サヌイ織物YouTubeチャンネル~それゆけ!博多もん!~
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
AIを難しく語らない。
私たちは中小企業のAI活用・導入をサポートする会社です。
九州・福岡のAI関連のおすすめ業者をお探しの方は、ぜひ弊社にもお問い合わせください。
キャンペーンや、経営者向けのマンツーマン無料AI講習も実施しております。
お気軽にどうぞ!
YENGIMON株式会社
福岡商工会議所 No.11-0149275 、福岡市ふくおか共創パートナー企業
https://www.yengimon.com/
X: https://x.com/yengimon
LINE: https://lin.ee/Z5V7t3f