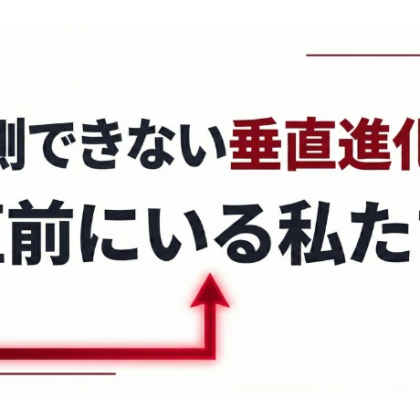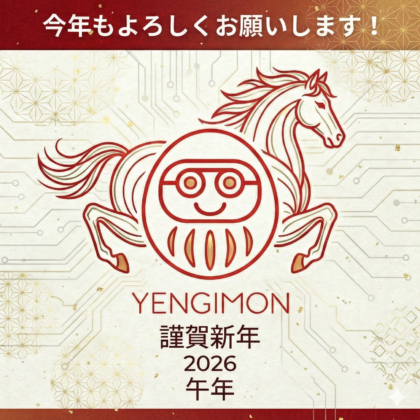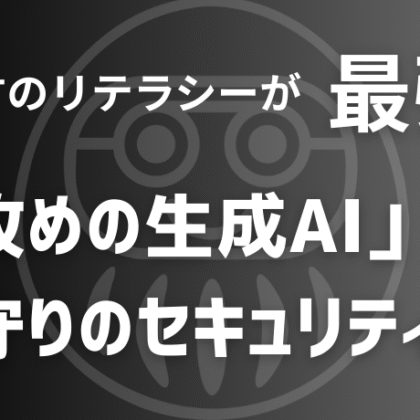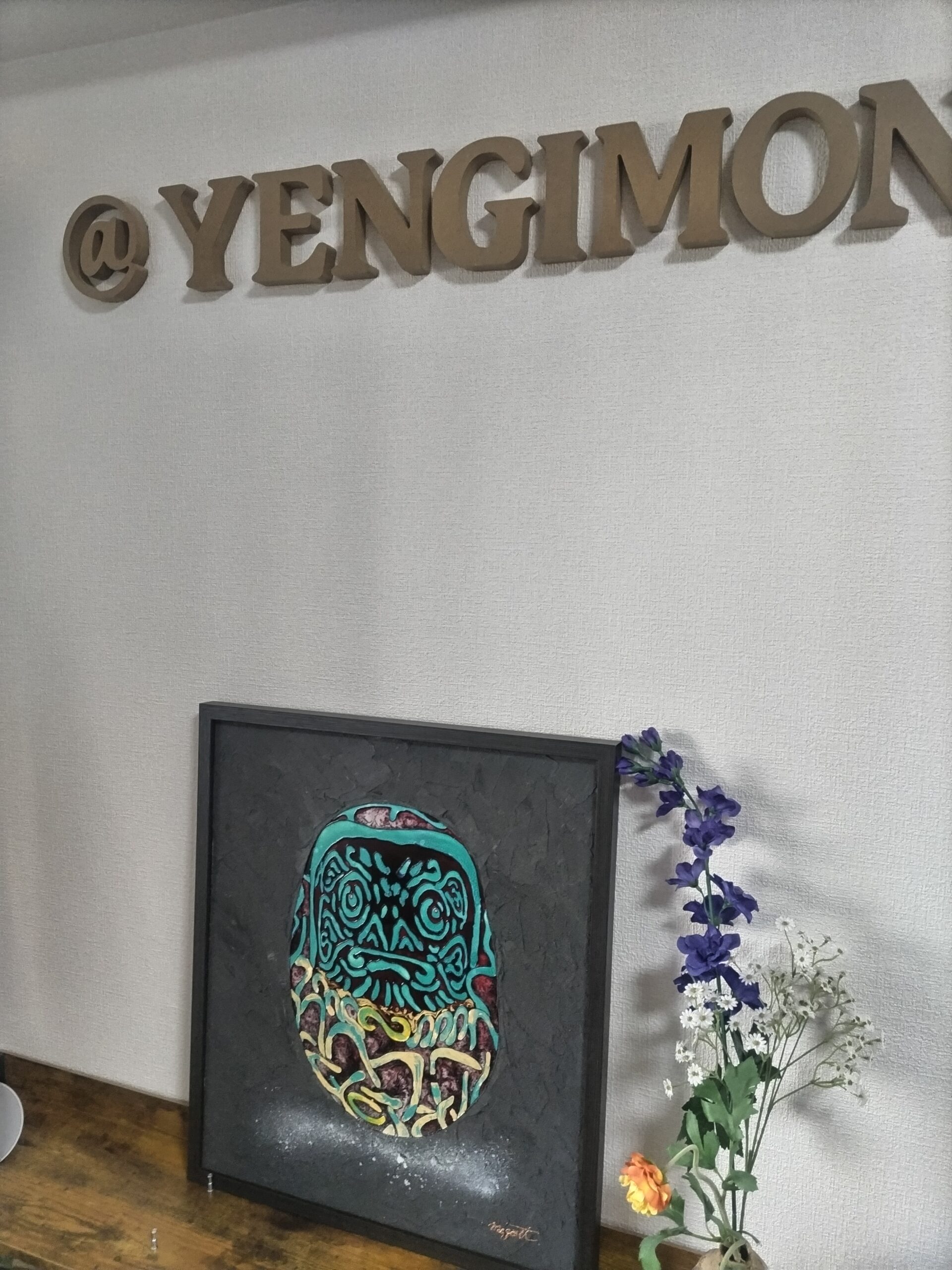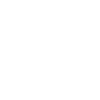はじめに
中小企業においては、限られた人員と予算の中で業務を効率化し、競争力を高めるための強力な選択肢となり得ます。
しかし現実には、「生成AIを導入したが期待した効果が得られなかった」というケースも珍しくありません。
原因の多くは、ツールそのものの性能不足ではなく、導入前の準備不足にあります。とりわけ、「どの業務にAIを適用するか」という選定を行うための業務分解が不十分なまま導入を進めてしまうことが、失敗の引き金になっています。
本記事では、生成AI導入を成功に導くために欠かせない「業務分解」の考え方と実践方法を、経営者・管理職の視点からわかりやすく解説します。加えて、新たに「細分類」という観点を取り入れ、現行ツールや作業方法まで掘り下げた分析手法をご紹介します。
なぜ業務分解が導入成功のカギになるのか
AIは万能ではない
生成AIは、万能な“何でも屋”ではありません。得意な領域と不得意な領域がはっきりしています。
AIが最も力を発揮するのは、繰り返し発生する業務、判断基準が明確な業務、データ化が可能な業務です。逆に、人間の経験や創造性、状況判断が欠かせない業務は、AIが置き換えるのではなく補助的に活用する形が中心になります。
導入効果を最大化するには、AIが得意な業務を正しく見極め、そこにリソースを集中させる必要があります。そのための基礎となるのが業務分解です。
○全体像を見える化して優先順位を決める
業務分解を行うことで、社内で日々行われている作業が一覧化され、業務構造が明確になります。
これにより、
- 無駄や重複作業の発見
- AI導入効果が高い領域の特定
- 導入順序の決定
といった判断がしやすくなります。
業務を大・中・小・細に分けるための視点
従来の業務分解は「大分類」「中分類」「小分類」の3階層で構成されることが多いですが、生成AI導入を検討する際には、さらに細分類(現行ツール・作業方法)を加えることで、導入計画の精度が格段に上がります。
- 大分類:企業活動の主要領域(例:営業、製造、経理、人事)
- 中分類:大分類をさらにプロセス単位で分割(例:営業活動の中の「見込み顧客開拓」「契約管理」)
- 小分類:具体的なタスクを動詞で記述(例:「請求書を発行する」「見積書を作成する」)
- 細分類:小分類を実行する現行手段(例:「Excelで作成」「銀行サイトから手入力」「紙伝票を使用」)
この「細分類」を設定することで、現状の非効率やアナログ作業を洗い出しやすくなり、AI化の優先度をより正確に判定できます。
業務分解の6ステップ
1. 業務をすべて書き出す
部署や役職を問わず、現場で行っている業務を網羅的に列挙します。重要なのは、「抜け漏れをなくすこと」。効率や順序は気にせず、とにかく全て出し切ります。
2.グルーピングと小分類化
似た性質の業務をグループ化し、その中で具体的な動作まで落とし込みます。小分類では必ず動詞を使い、曖昧な名詞だけで終わらせないことがポイントです。
3. 細分類で現行方法を特定
小分類ごとに、どのようなツールや手段で実行しているのかを細分類として記録します。これにより、AI化する際の置き換え対象や導入効果を数値化しやすくなります。
4. 業務フロー化
小分類と細分類を時系列順に並べ、業務フローを作成します。前後関係や依存関係が見えることで、改善ポイントや自動化の余地が明確になります。
5. 時間と頻度の記録
各作業の1回あたりの所要時間と月間頻度を記録します。現行手段の効率性も併せて評価すると、削減インパクトの大きさが予測できます。
6. AI導入候補を選定
3条件(繰り返し発生・ルール化可能・データ化可能)に基づき、AI化すべき業務を選び出します。この時、細分類の情報があると優先度の判断がより的確になります。
生成AI導入に適した業務の特徴
●繰り返し発生する業務
例:日報作成、定型メール送信、商品データ入力。
頻度が高く、ルーチン化されているほど効果が出やすい。
●判断基準が明確な業務
例:請求処理、在庫補充判断、フォーマット化された契約書作成。
誰が行っても同じ結果になる業務はAIが得意。
●データとして扱える業務
紙や口頭でなく、デジタルデータを利用できる業務が前提。
必要に応じてOCRやデータベース化で前処理を行う。
分類の活用例
| 大分類 | 中分類 | 小分類 | 細分類(現行方法) | 頻度 | 時間 | AI化可否 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経理 | 請求処理 | 請求書を発行する | Excelで作成しPDF化 | 月10回 | 15分 | ◎ |
| 営業 | 提案業務 | 提案資料を作成する | PowerPointで手作業 | 月8回 | 60分 | ○ |
| 製造 | 品質管理 | 検査記録を入力する | 紙伝票を手入力 | 週5回 | 20分 | ◎ |
このように細分類を入れることで、現行ツールの限界やアナログ作業の割合が一目でわかります。
効率化は目的ではなく、その先のための手段
業務効率や品質向上は重要ですが、それ自体がゴールではありません。
生成AI導入の本当の価値は、
- 自社の競争力を持続的に高め、売上を向上させる
- 人と組織が、より価値の高い活動に時間を振り向けられる環境を整えること
にあります。
AIは時間を生み出すためのツールに過ぎず、その時間をどう使うかこそが企業の成長を左右します。
導入の進め方とコンサル活用
中小企業が生成AIを導入する際は、まず影響範囲の小さい業務から始め、効果を測定しながら段階的に広げることが重要です。社内に専門知識が不足している場合は、生成AIの活用に詳しいコンサルタントと連携し、適切な業務分解と導入設計を行うことで、失敗リスクを大幅に減らせます。
まとめ
生成AI導入を成功させるための最大のポイントは、「業務分解」です。
さらに細分類まで踏み込み、現行ツールや作業方法を明らかにすることで、導入効果の予測精度が高まり、優先順位付けが的確になります。
効率化はあくまで手段であり、その先にある競争力強化や価値創出こそが最終目的です。
経営者・管理職の皆さまには、この視点を持って生成AI導入を戦略的に進めていただきたいと思います。
無料40分オンライン相談のご案内
YENGIMON株式会社では、中小企業の生成AI活用を推進する為、業務分解を支援しています。
まずは無料40分オンライン相談で、貴社に最適な活用方法をご提案します。
お気軽にご連絡ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
AIを難しく語らない。
私たちは中小企業のAI活用・導入をサポートする会社です。
九州・福岡のAI関連のおすすめ業者をお探しの方は、ぜひ弊社にもお問い合わせください。
キャンペーンや、経営者向けのマンツーマン無料AI講習も実施しております。
お気軽にどうぞ!
YENGIMON株式会社
福岡商工会議所 No.11-0149275 、福岡市ふくおか共創パートナー企業
https://www.yengimon.com/
X: https://x.com/yengimon
LINE: https://lin.ee/Z5V7t3f