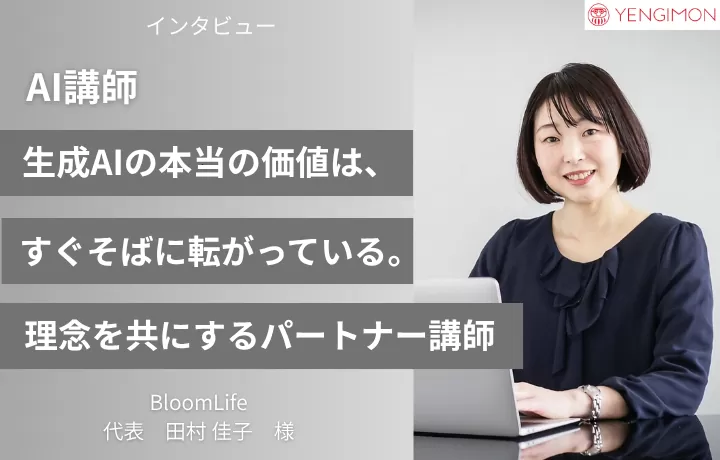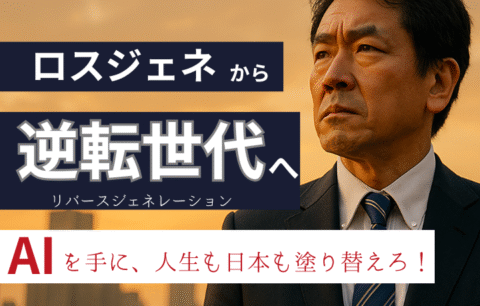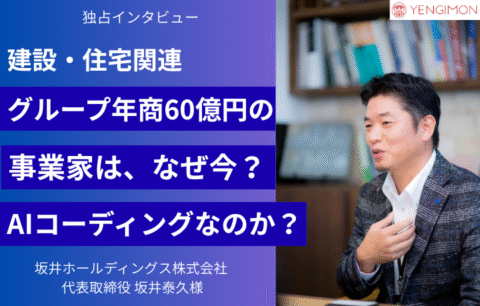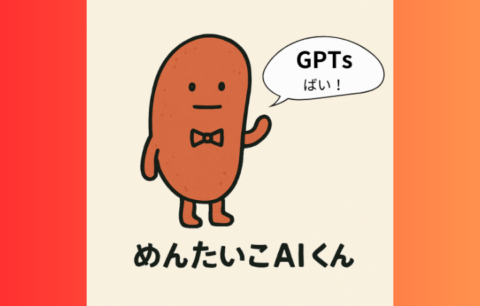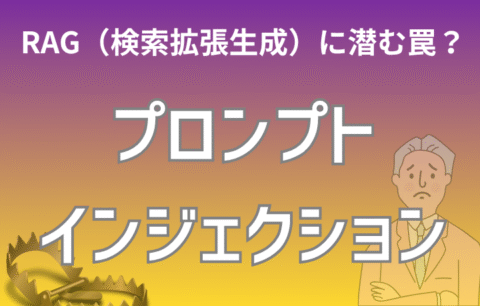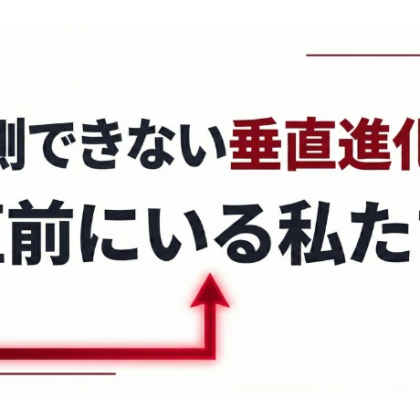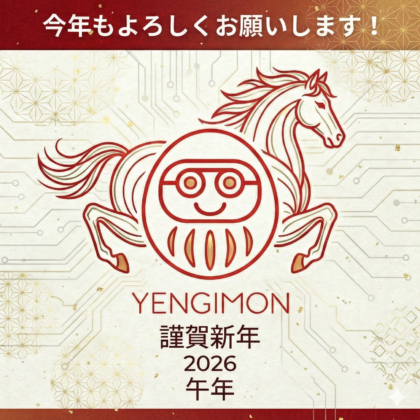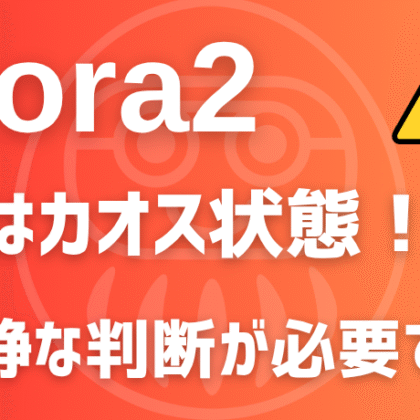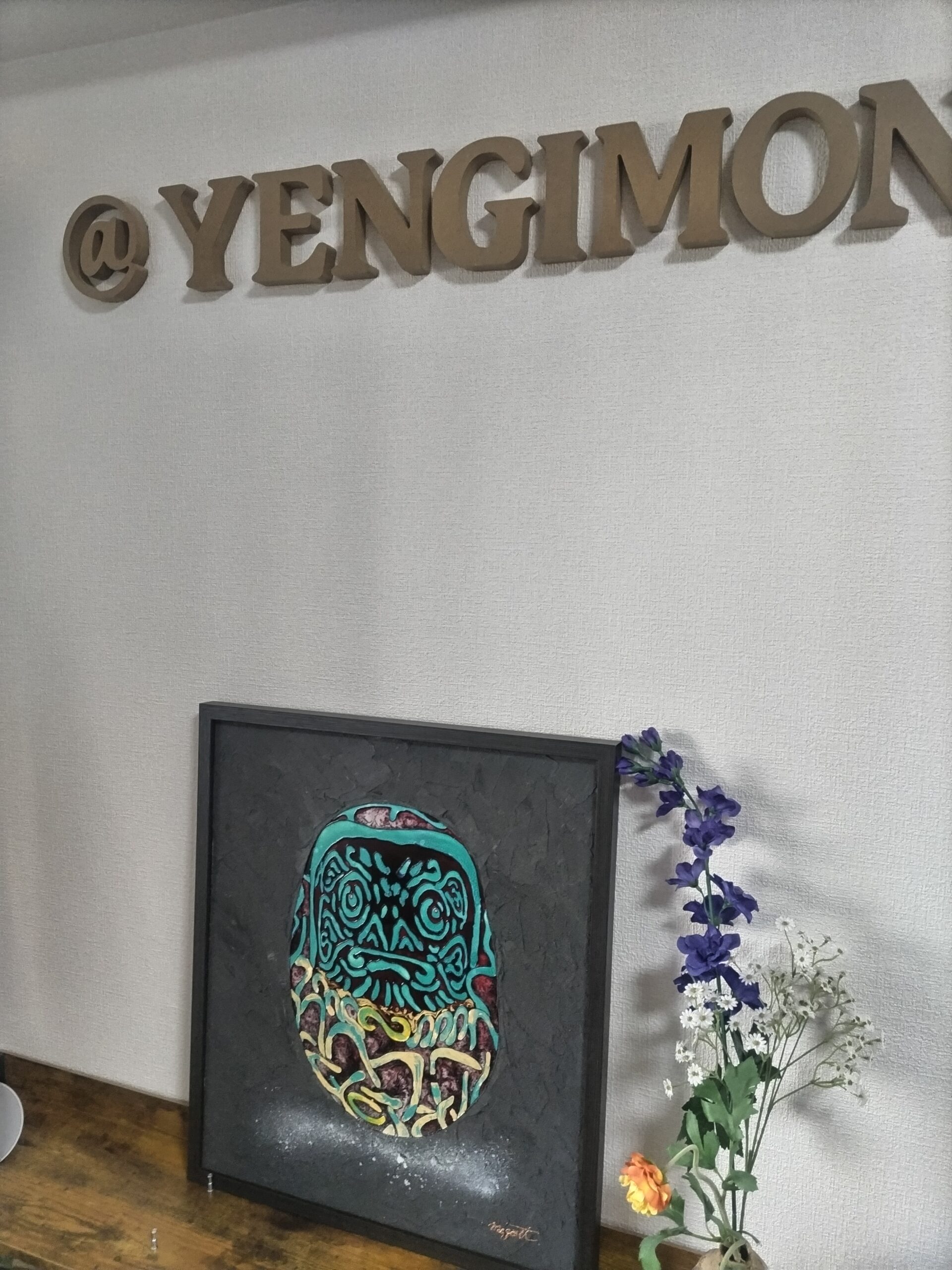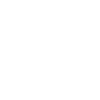今回はYENGIMONのパートナーとして、
生成AIの研修を全国の中小企業に行っているAI講師・Bloomlife代表 田村佳子氏を特集する。
「AIの学びは、難しいことを簡単にするためのものではなく、
“人と仕事を楽にする”ためのものです。」
彼女の言葉には、経験に裏打ちされた温度と誠実さがある。
この記事では、田村氏のキャリアの軌跡から、AI講師としての見解、
そしてYENGIMONとの信頼に基づく協業のあり方までを紐解いていく。
- 第一章:支えることから始まったキャリア「秘書」という原点
- 第二章:講師業への第一歩「伝えることの楽しさ」に気づいた日
- 第三章:コロナ禍の転機「在宅勤務」と“老犬との時間”が導いた再出発
- 第四章:YENGIMONとの出会い「歩幅を合わせてくれる」会社
- 第五章:AI講師という仕事「面白そう」と思わせる力
- 第六章:中小企業の現実“新しいもの”への抵抗をどう乗り越えるか
- 第七章:YENGIMONの支援体制「品質チェックがある安心感」
- 第八章:AI活用の現在地と未来そして自らのスキルアップ
- 第九章:AI人材のこれから“変化に対応できる人”が生き残る
- 第十章:協業先としても安心「同じ目線で歩ける会社」
- 「AIを難しく語らない。」モットーで中小企業の進化を支える
第一章:支えることから始まったキャリア
「秘書」という原点
田村氏の社会人としての第一歩は、某有名飲料メーカーの役員秘書だった。
企業の中枢で経営陣を支えながら、常に“相手が何を求めているか”を察する力を磨いてきた。
「社会人生活は役員秘書から始まりました。
その後、民間企業や官公庁、外郭団体などで、正社員・派遣・嘱託・パートといろんな働き方を経験しました。
どんな立場でも、常に“サポートする側”だったと思います。」
営業事務や総務事務など、裏方としての業務を幅広く経験。
だがその“支える”仕事の延長線上に、のちの講師業へとつながるターニングポイントがあった。
第二章:講師業への第一歩
「伝えることの楽しさ」に気づいた日
転職の合間、田村氏は職業訓練校に通っていた。
修了後、講師のサポートを依頼された。
「最初はサブインストラクターとして、30〜40人規模のウェブデザインコースに入りました。教えるのは初めてでしたが、受講生が“わかった”と笑顔になる瞬間が楽しくて。あれが講師業の原点です。」
「引き継ぎが“分かりやすい”と褒めてもらうことも多かったので、
“人に伝える”ことへの苦手意識はなかったですね。」
その後、福岡の製造から通信販売までを行う食品会社に転職。
そこで新卒採用と新人研修を担当したことが、さらに“教えること”への関心を深める。
「事務仕事よりも、研修が楽しかったんです。」
この時期から、彼女の中に「わかりやすく伝える」という軸が形成されていく。
それはのちに、AI講師としての最大の強みとなる。
第三章:コロナ禍の転機
「在宅勤務」と“老犬との時間”が導いた再出発
2020年、世界が大きく変わった。
コロナ禍、田村氏もまた働き方を見直すことになる。
「当時、飼っていた犬は介護の必要があったんです。
犬のそばにいたいという想いと、リモートワークが一般化した時代。
在宅で働ける仕事を探して、業務委託のバックオフィス業務に切り替えました。
結果的に、19歳になるまで共に過ごせたのは、本当にありがたかったですね。」
その静かな時間の中で、心の奥にあった“新しいことへの好奇心”が再び動き出す。
「このままでは、事務職はAIに仕事を奪われるかもしれない。
そう思って、AIを学び始めたんです。」
最初に触れたのはChatGPT。
だが、思うように使いこなせなかった。
「質問が下手で、出てくる答えもピンとこない。
でも、Midjourneyに出会ってから一変しました。
“絵が描けない自分でもイラストが作れる”って、本当に感動しました。」
さらにリサーチにはPerplexityを使うようになり、新しい検索の形を見た。
「AIが何でも相談相手になってくれる。 そんな実感がありました。」
第四章:YENGIMONとの出会い
「歩幅を合わせてくれる」会社
YENGIMONと出会ったのは、AIコミュニティ「Shift AI」でのオフ会だった。
「“どんな仕事に興味がありますか?”と聞かれて、
何気なく“講師をやってみたいです”と口にしたんです。
そのとき、“ちょうど講師を探している”と。まさにご縁でした。」
田村氏はYENGIMONのモットー「AIを難しく語らない」に強く共感した。
「AIって、どうしても専門用語が多くて、初心者には近寄りがたいんです。
でも、YENGIMONさんは“そばで一緒に歩いてくれる”ような会社だと思いました。
寄り添うというより、“歩幅を合わせる”という表現がぴったりなんです。」
その「歩幅を合わせる」という言葉は、
後に両者の協業を象徴するキーワードとなった。
第五章:AI講師という仕事
「面白そう」と思わせる力
AI講師としての田村氏の講義は、
単なる技術講習ではない。
「受講者が“面白そう”“やってみよう”と思えることを大切にしています。
知識を詰め込むより、身近な課題にどう使えるかを想像してもらう。
そこにAI学習の本質があると思っています。」
印象的な講座がある。
テーマは「忘年会の自動化」。
Googleフォーム、スプレッドシート、条件付き書式、関数、Googleサイトを組み合わせ、
忘年会の出欠・金額・会場情報を完全自動化し、自然とAIツールを覚えられるというプログラムだ。
ゴール設定は、「忘年会の席に着いた時点で、全員分の最初の1杯が並ぶ」こと。
「“面倒くさい”を“なくす”ことが、AI導入の第一歩なんです。
特別な技術より、まず“これ便利!”と感じてもらうことが大切ですね。」
このユニークな講義は、受講者だけでなくYENGIMONをも唸らせた。
「忘年会の自動化」という一見ユーモラスで身近な題材が、実はAIによる業務DXの縮図だったからだ。
第六章:中小企業の現実
“新しいもの”への抵抗をどう乗り越えるか
AI導入が進まない理由を尋ねると、田村氏は静かに答えた。
「AIに限らず、“新しいものへの抵抗感”が本当に強いです。
当然ですけど、皆さん忙しいですし、長年慣れたやり方を変えるのは不安で、
担当者にとっては“負担が増えるだけ”に見えてしまう。」
しかし、導入後の効果を目の当たりにすると、その不安は一気に変わる。
「AIを使うことで、確実に後が楽になります。
一度体感すると、もう戻れないという声も多いです。」
講師として意識しているのは、抵抗感を“安心感”に変えること。
「身近に感じてもらうこと。 “あ、これならできるかも”と思ってもらうこと。
それが講師の役割だと思っています。」
第七章:YENGIMONの支援体制
「品質チェックがある安心感」
YENGIMONのパートナーに対してのサポート体制について田村氏はこう語る。
「講習前にクライアントとの打ち合わせに同席させてもらえたり、
内容のすり合わせや資料のチェックもしていただける。
さらに講義後の録画も確認してもらえて、
“伝え方の品質”まで見てくださるのは本当に心強いです。」
単に“案件を渡す”関係ではなく、
“同じ目線で育てていく”パートナーとしての姿勢。
それこそが、田村氏がYENGIMONに寄せる信頼の理由だ。
第八章:AI活用の現在地と未来
そして自らのスキルアップ
田村氏が今もっとも注目しているのは、Google Workspace。
「講師の仕事のために勉強したら、
“なぜ今まで使っていなかったんだろう”と思うほど便利でした。
スプレッドシート、ドキュメント、スライド、フォーム――
全部がつながっていて、ひとつの“チームOS”みたいなんです。」
Google Workspaceを企業導入する際に役立つ管理者向けの資格であるAssociate Google Workspace Administrator (AGWA) も取得した。
AIを活用するためには、まず安全な環境が必要。
その意味で、Google Workspaceは、使用者が入力した情報はデータ学習に利用されないことが約束されており、
中小企業のDXの出発点としては、おすすめツールの1つだ。
第九章:AI人材のこれから
“変化に対応できる人”が生き残る
AI業界の3〜5年後をどう見ているかと尋ねると、
田村氏は少し考えて、こう答えた。
「変化が速すぎて、正直5年先は読めません。
でも、“変化に対応できるかどうか”が生き残りの鍵だと思います。」
特定の技術やツールに固執するのではなく、
“必要なものを、必要なときに取り入れる柔軟性”。
「AIは固定的なスキルじゃなく、“変化とともに進化する力”だと思います。
だからこそ、“今の自分の仕事にどう使えるか”を常に考えることが大切です。」
第十章:協業先としても安心
「同じ目線で歩ける会社」
最後に、YENGIMONと協業して感じたことを尋ねると、
田村氏は静かに、しかし確信を持って言葉を選んだ。
「取引先の企業だけでなく、
私のようなパートナーにも同じ歩幅・同じ目線で接してくださる。
だから安心できるし、“一緒に頑張ろう”と思えるんです。」
YENGIMONは、AI技術を通じて“人との信頼関係”を大切にする会社を目指す。
AIを扱う企業の中で、この“気遣える人間味”こそが最大の強みだ。
「AIを難しく語らない。」
モットーで中小企業の進化を支える
AI導入は、技術ではなく文化の変化だ。
YENGIMONと田村氏が互いに共感し合えたのは、
“その人の歩幅で生成AI活用を進める”という一見遠回りに見えるモデルである。
福岡から全国へ。
中小企業がAIを“現実的に使いこなす”未来は、もう始まっている。
その現場には、信頼でつながる協業の形がある。
Thank you by
Bloomlife 代表 田村佳子さん
「PC業務サポート」でサポートさせていただきます。
https://bloomlife.work/
—————————————————————————————————–
私たちは中小企業のAI活用・導入をサポートする会社です。
九州・福岡のAI関連のおすすめ業者をお探しの方は、
ぜひお気軽にお問い合わせください。
また、パートナー・協業(開発、コンサル、講師など)のご提案も歓迎です。
YENGIMON株式会社
福岡商工会議所 No.11-0149275 、福岡市ふくおか共創パートナー企業
HP:https://www.yengimon.com/
X: https://x.com/yengimon
LINE: https://lin.ee/Z5V7t3f